事前情報の正確さが、緊急輸送の命を握る
K・M / N・T
ドライバー/配車担当
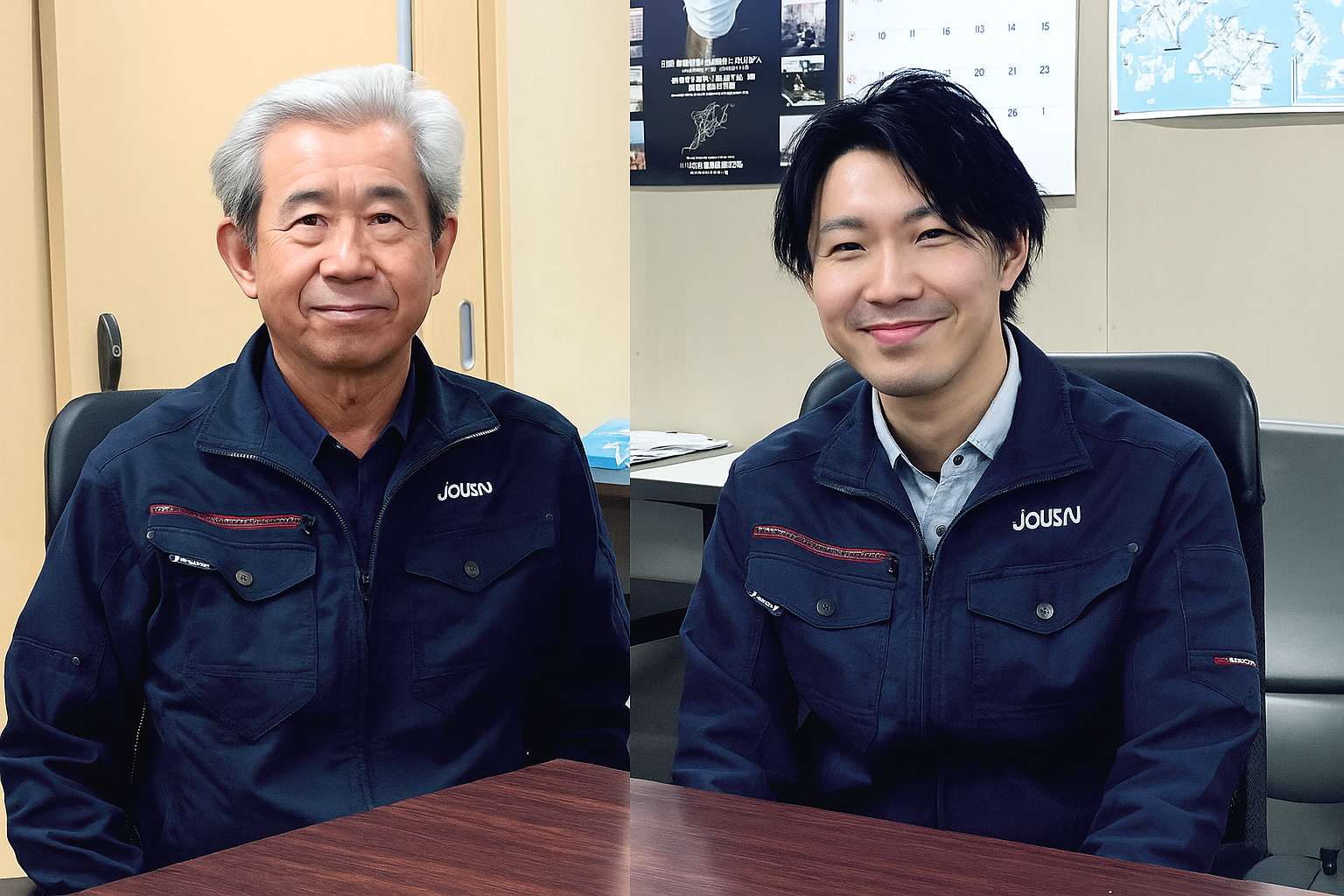
Q1.平時から災害時対応の取り組みはしていましたか?
平成23年の東日本大震災の際、私たちは3月13日に宮城県仙台市へ緊急物資の輸送を行いました。この時の対応は社内でも記録として共有され、後の全体会議やグループ長会議などでも、有事の際の行動や連絡体制について議論するきっかけとなりました。
こうした災害対応の体制自体は、実は震災前から整備されていましたが、実際に本格的に運用されたのは東日本大震災が初めてだったと記憶しています。
Q2. 会社からの輸送指示があったのはいつ頃ですか?
1月2日午前10時、所属長から「石川県トラック協会を通じて、県から緊急輸送の依頼があった」と連絡を受けました。輸送内容は、飲料水やパンなどの食料、そして発電機などの物資です。
その日の午後には石川県産業展示館で積み込み作業を行い、穴水町や能登町へ向けて出発しました。自分の地元で起きた大きな災害ということもあり、「一刻も早く物資を届けたい」という強い思いで出発しました。
Q3. 運行前に準備したモノは、ありますか?
発災から2日目で、災害の全体像はまだ把握できていませんでしたが、道路の被害が大きいことだけは分かっていたため、渋滞の発生が予測されました。
そこで、東日本大震災の経験を活かし、緊急物資輸送車両の証である「緊急物資輸送車両標章(通称:マル緊マーク)」の申請を行い、交付を受けました。
石川県産業展示館に到着すると、館内には仮設の本部のような拠点が設けられており、すでに1台のトラックが到着していて、パンの詰め合わせ作業が行われていました。
その後、自車への積み込みを開始しましたが、初動の混乱もあり、出発までにはかなりの時間を要しました。
また、当社では「被災地では現地調達がほとんどできない」と予想し、パン・おにぎり・飲料水などの食料をあらかじめ車両に積み込んで備えました。
Q3. 出発の際、道路情報などは十分に収集できていましたか?
報道やネット情報、配車担当から可能な限り情報を収集しましたが、被災地に近づくにつれて、予想以上の被害の大きさを実感しました。また、事前に得ていた情報とは大きく異なっていました。
Q4. 現地までの道路状況などは。また、輸送中はどのようなことに注意しましたか?
まず何よりも「確実に届ける」ということを最優先に考え、「慌てず」「急がず」「パンクやバーストを避ける」ことを意識して、慎重な運転に集中しました。
道路は段差や亀裂、陥没がひどく、乗用車でもタイヤがバーストして立ち往生している車両が多く見られました。通行できるルートが限られている中で、立ち往生は他の車両の妨げになってしまいます。トラックは簡単には止められないため、必死の思いで運転しました。
今回の運行には配車担当者が同乗しており、被災地内では二人で道路の損傷状況を確認しながら、本社に連絡を取り、現地で得られない情報を聞いたり、う回路を探すなど、あらゆる面でサポートしてくれました。何より、隣にいてくれるだけでも大きな安心感があり、ツーマン運行はとても心強かったです。
また、現場での荷卸し作業についても課題がありました。被災地では1人でも多くの人手があれば、それだけ早く作業が進みます。ドライバーは危険を承知のうえで被災地まで運転してきているため、できれば体力を使う荷卸しは避けたいところです。
Q5. 輸送中に想定外の問題は起こりませんでしたか?
産業展示館から出発する際、積み込み作業は「到着先でトラックを横付けして、ウイングを開いて荷卸しする」ことを前提に行っていました。ところが、実際に到着した2次集積拠点では、後方からホーム付けしなければ荷卸しできない施設だったため、作業に非常に時間と労力がかかってしまいました。
非常時には時間も体力も無駄に消耗できない状況です。そのため、事前の情報の正確さがどれほど重要かを痛感しました。
また、すべての地域で携帯電話が通じるわけではなく、本社や地元の知人に連絡を取ろうとしても「電話が繋がらない」状況に直面することもありました。そんな時は、すれ違う他のドライバーに聞き込みをして情報を交換することもありました。どうしても最新で正確な情報が必要な場合は、携帯の電波が届く場所を探して移動したこともありました。
Q6.今回の緊急物資輸送の反省点や、今回の経験を踏まえて他のドライバーに伝えたいことは、ありませんか?
今回の経験を通じて、「情報の正確さ・大切さ」を強く実感しました。
また、一般車両が大量に被災地へ流入したことで、緊急物資を運ぶトラックの機動的な輸送が妨げられてしまったことは、とても残念に感じました。
今後、緊急物資輸送に関わる方々には、平時から社内会議などを通じて、有事の際の対応体制の強化や、情報収集の方法についてしっかり話し合い、備えておくことの重要性を伝えたいと感じています。


